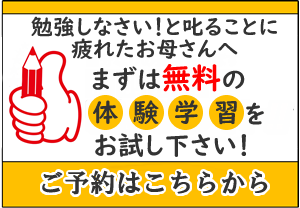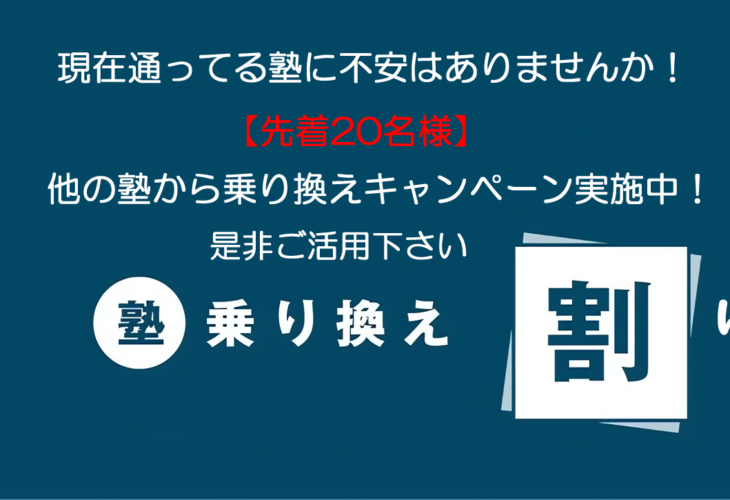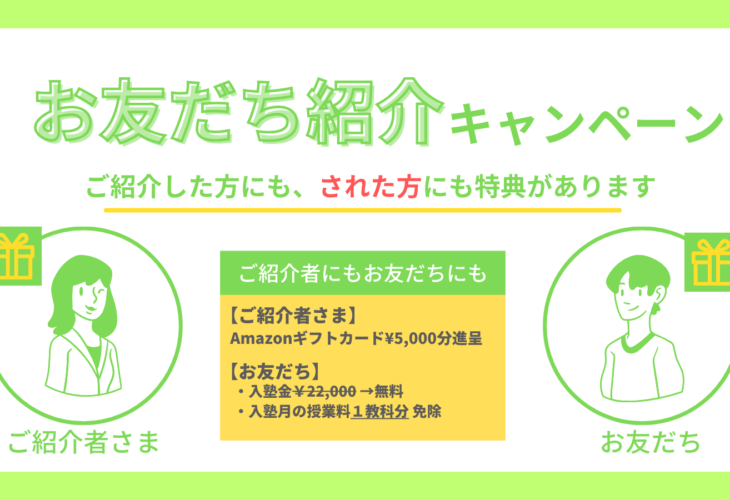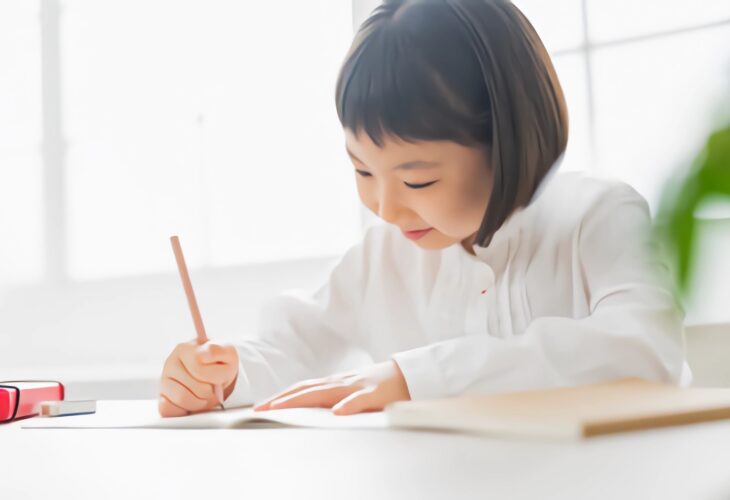腰に褌(ふんどし)を着けた2人が、土を入れた俵を円形に敷き詰めた土俵の上で相手を押したり投げたりして、土俵の外に出すか、土俵に足の裏以外をつけさせて勝敗をつける。あなたはそんな相撲が好きですか?自分が相撲するわけじゃないんですけれども(笑)。
ご存知のように相撲は国技。古事記、日本書紀の頃からあった日本の代表的な伝統文化、観衆の前で相撲が行われた様子が描かれた浮世絵なんかも残っています。
野球やサッカーのような団体戦でなく個人戦、両力士の呼吸が合って勝負を始める、呼吸が合った立ち合いはきれいです。
あっという間にケリがつきます。1日に行われる取組の数は、幕内:21、十両:14、幕下30、三段目50、序二段53、序ノ口14で、朝8時から午後6時まで、なんと182戦もあります。
柔道やボクシングなどのように、体重ごとに階級が分けられていない。体重200kgを超える力士と100kgぐらいの体重しかない力士で取組(試合)が行われる
成績によって格付けされ、その格付けによって給料や待遇だけでなく、服装まで決まる。負けると横綱から大関、大関から関脇と転落します。
勝敗はメンタルで決まります。相手Bは突っ張りで来るだろうからAはそこを、”いなし”と”引き”でチャンスを探ろうとするな、力士がどういう気持ちでその場を決するのか、自分だったらどうするだろう?そこが見どころです。観客も見ていますからね。
その中で大の里と言う力士は、ここ2場所ほど成績が良くなかった。彼が今回の春場所に向けて言った言葉が一日目に勝って、全勝につなげたいと言っていました。つまり1学期の中間テストで良い成績を取れば、自信と、喜びをキープしたくなって、その後1年間は自動的に高成績にしていくのと、似ている。
女子高校生の話です。TheJukuで土曜日にフォレスタで数学をやっていて、最初はなかなか進まなくて質問もミスも多かった。ところが、2年生になって急にマルが増え、質問もミスも少なくなった。で、どうしたのか聞いたら、友達に質問されるようになってから、めちゃ成績が伸びたと言うんです。
教えると自分の成績が上がる。生徒に教えるようになったら、新しい単元に入っても友達に聞かれるだろう、そこで分かりませんと言うのもシャクだから、先回り、予習して頑張る。
二つの例は、嫌な勉強でもつい欲が働いて自動的に勉強するコツです。やればやるほど、やることが減るどころか増える、やればやるほどやりたくなるんです。