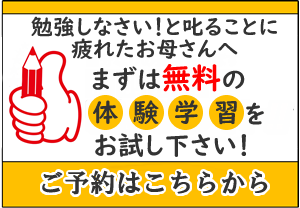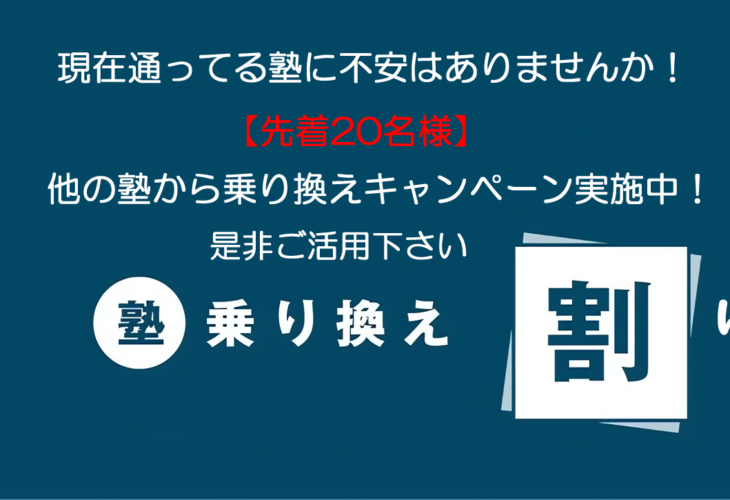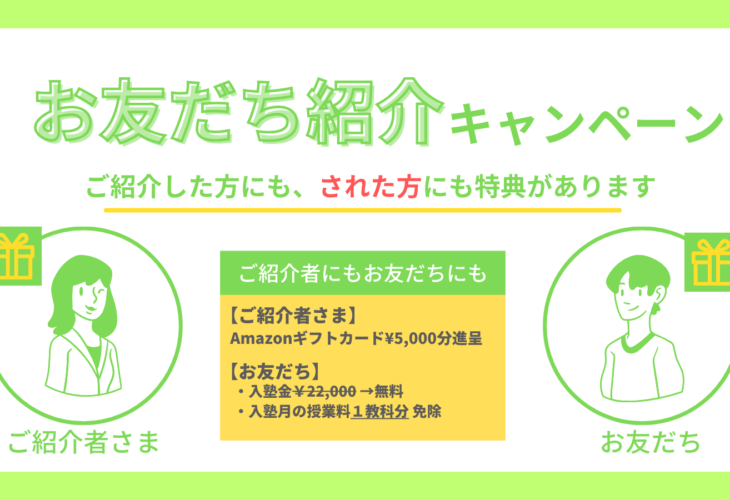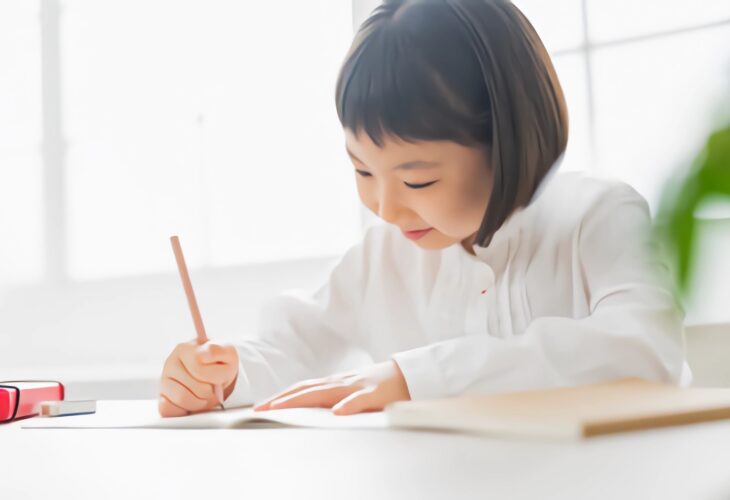桜がまぶしい日曜日のお昼のこと、ぶらっと1号線を走っていたら、車窓から見えてきたのは、10枚ほどの段ボール箱を親子2人が破棄する姿でした。小5ぐらいの女の子がお父さんと一緒に古新聞倉庫に段ボールを投棄している、そんな姿を見て「ハハ〜ン、彼女はきっとお父さんのことが好きなんだ!」と思いました。
ところで、新学期、英語や数学だけでなく理科や社会も覚えることがたくさんあります。歴史の流れや電流の公式が覚えられない。好きなら、問題ないんです。ところが、苦手だとしたら、テストの時だけ無理して覚える。けれども、テストが終わったらすっかり忘れる、「何やってたん?」と自問したり「あれってなんやったん?」って自戒することになります。塾長なんか、あとでやろう、いつかやろうって、思っていた歴史や電流、いまだに できないです。トホホ(涙)
ところで、”しちはごじゅうろく”とか、九九は一瞬で答えますよね。九九をあなたは、どうやって覚えました?塾長は2の段、3の段とかを何十回、何百回と声にだして覚えました。小学校2年生の3学期、算数の授業は、覚えた九九をみんなの前で発表することになっていたんです。
家で覚えてきた九九を競うように毎日、教檀に立って発表する。1日1段だけ、飛び段なし、つっかえたら翌日やり直し、2の段から9の段まで言えた人が優勝!というルールでした。
クラス中大騒ぎとなって、普段おとなしい女子なんかが、その日のトップを走る有段者となってみんなから絶賛されたわけです。臆病な塾長はまごまごしていたら最下位です。ハ〜?。(汗)
あの「九九」を覚えることですら、あんなに大変だったので、たくさん覚える今の子は、さぞ、大変だろうと思います。
社会人になって、当時、算数・数学の公文式に入社しました。公文公(くもんとおる)さんの長男が、「九九を、そんなふうに暗記して覚えた記憶、あれへん」と公言します。え〜、どうしたん?
お馴染みの、かけ算「九九の表」を手元に置いて、問題を解く時それを見ながら解いた、解いていくうちに、自然と覚えた、というんですね。へぇ〜、楽じゃん!
小学生が「たし算」をするのに最初は指を使います。たし算でくり上がりがあると指を使う。二桁のかけ算でくり上がりがあると指を使う。慣れてくると指を折るのもめんどくさくなって自然に使わなくなる。かけ算「九九の表」もこれと同じ理屈だと思った。
解くときに、表を作って、何回も使う、という暗記法です。例えば、歴史の流れを覚える時は、ダジャレかなんかで一気に覚えるというよりも、年表を作って、それを何回も見ながら問題を解いていく、電流も、公式を表にして、問題に出てくる数字を当てはめる、すると知らないうちに解き方をおぼえてしまう。理科や社会の分厚い教科書なんか、重要語句をマジックで塗りつぶしてくり返し音読する、そうすると覚える。
なぜ、この場に及んでこんな話かというと、FXです。乱高下する株価をテンプレートで押さえ込むことができるんじゃないか、そう思ったんです。テンプレートを作って、数字を入れていく、使い慣れていくと知らないうちに勝ってる。これってすごくない?と思うんです。
ですが、どんな優れた方法も弱点があって、せちがない世の中ですから、すぐに結論が欲しい人にはまどろっこしいかもしれません。作っただけで安心して、そのまま寝てしまう、という徒労リスクもあります。
まぁ、いずれにしても、時間がかかるし、たくさん問題を解かなきゃいけないけれど、イヤイヤ無理して中途半端に覚えて後悔するより、表とか空欄を使って、くり返しやって、好きになって、慣れて、知らないうちに脳に刻み込まれていく、これは、ラクに記憶し、ラクに呼び戻す、いい方法だと思います。