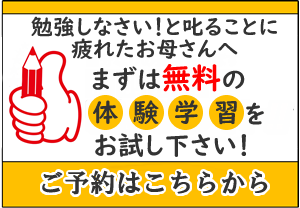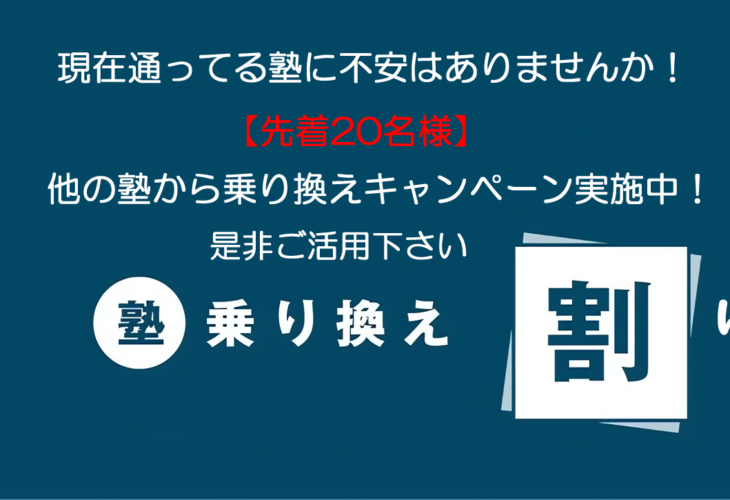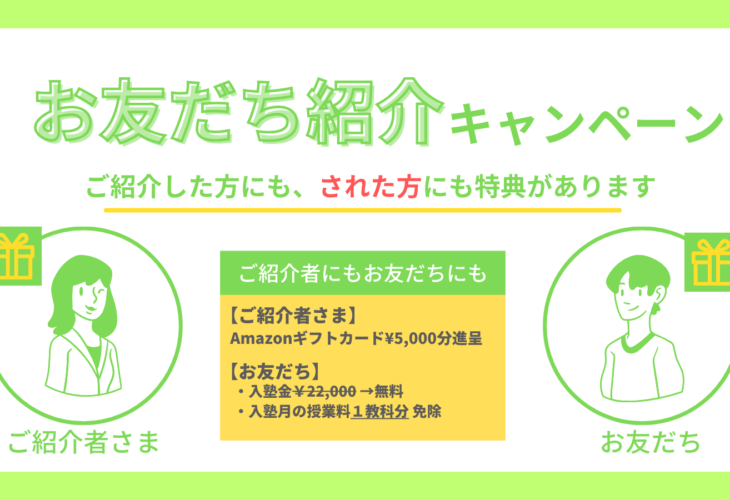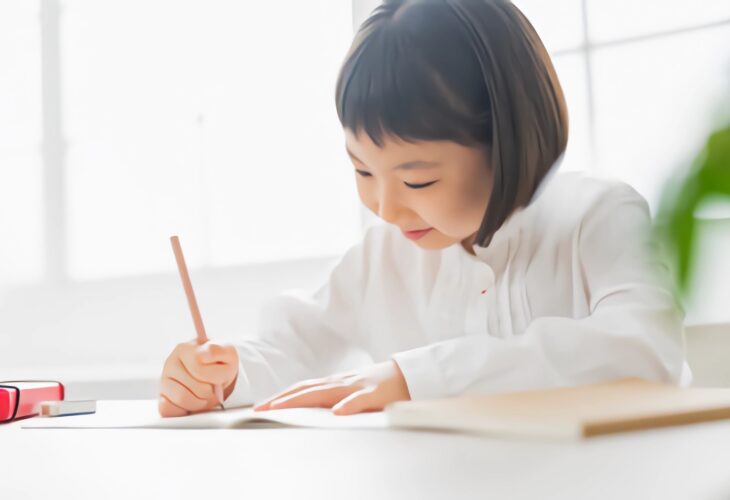理由は大きく分けて2つあります。
①先生の働き方のため
今、学校の先生たちはとても忙しくて、授業の準備や生活指導だけで手いっぱいです。
部活は本当は学校の義務ではありませんが、ほとんどの中学校で行われ、先生が顧問として担当しています。
でも、中にはその部活を経験したことがなく、十分な知識がないまま指導している先生もいます。
「残業を減らす」「家庭と仕事の両立を大切にする」ことが求められている中で、先生の善意だけに頼るやり方は続けられなくなってきたのです。
②学校の規模が小さくなったため
子どもの数が減り、1つの学校だけではチームが作れない競技が増えています。
たとえば、野球やサッカーのように人数が必要な競技では、複数の学校が集まってチームを作る「拠点校方式」が広がっています。
子どもたちが放課後にスポーツや文化活動を楽しむ場所はなくせません。そこで国は2023年から、まず休日の部活を「地域の指導者」にお願いする取り組みを始めました。
改革はうまくいっているの?
まだ道半ばです。
国の調査では、地域移行の計画を立てている自治体は全体の半分くらい。全国には約7万2000の運動部、約2万3000の文化部があり、すべてを地域に移すのはとても大きな挑戦です。
一方で、神戸市のように来年の夏で学校の部活をやめて、地域クラブ「コベカツ」に完全に移す自治体もあります。
ただ、そこまで踏み切った自治体はまだ少なく、多くは様子を見ている段階です。
どんな課題があるの?
一番の課題は「受け皿づくり」です。
地域クラブを運営してくれる団体や、子どもに教える指導者を集める必要があります。
スポーツ協会やスポ少、民間クラブ、退職した先生や経験者など、さまざまな人の協力が不可欠です。
さらに問題はお金です。学校の部活は無料でしたが、地域クラブは会費が必要になります。
「会費はいくらにするのか」「どのくらい公費で助けるのか」などを国や自治体が決めていく必要があります。
また、活動場所や生徒の移動手段、大会の運営、事故が起きたときの対応や保険、体罰やハラスメントを防ぐための研修など、多くの課題が山積みです。
どんな良いことがあるの?
地域に移すと活動の幅が広がります。
神戸の「コベカツ」では、野球やサッカーだけでなく、eスポーツ、太極拳、ヨガ、農業、国際交流など多彩な活動が始まりました。
子どもたちは「大会を目指す真剣な活動」だけでなく、「健康づくり」や「友だちづくり」など、ゆるやかな参加も可能になります。平日と休日で違う活動を楽しむこともできます。
先生たちも、地域のクラブに指導者として関わることができ、授業の準備時間を確保しやすくなります。これによって授業の質が上がり、先生という仕事に就きたい人も増えることが期待されています。
お父さんやお母さん、お祖父さん、お婆さん、地域の役割
指導者不足を補うために、保護者が「見守りスタッフ」として参加する例もあります。
神戸市では吹奏楽部の代わりに保護者が楽団を立ち上げました。
また、大学生や企業も指導に関わる仕組みが広がっています。特に平日の指導は学生に期待されています。
まとめます
部活動の地域移行は、簡単なことではありません。
でも、子どもたちの放課後を守りつつ、先生の働き方を改善するためには避けて通れない改革です。
地域・保護者・学校が協力して進めることで、より多彩で安心できる活動の場をつくることができます。
<9/6日経より>
部活が内申点として評価の対象になるか、ならないか、ということよりも
塾長が思ったのは地域に移すことで、部活が子どもにとって将来のイメージ形成に
大きく影響することです。
地域の大人と交わることで、仕事やキャリアにおいて「こんな人になりたい」と思える相手に出会う、そして
具体的なスキルや学習への取り組み方などを学ぶチャンスです。
昔、海陽中学を受験する生徒がいて、愛知県蒲郡市まで行ったことがあります。
ここは全寮制で、定期的に先輩との交流会が催されています。
担任の先生からうかがったのは、毎回、ゲストが医師やパイロット、
トヨタの社員、弁護士といった先輩が登壇して、勉強の苦労話や今の仕事について
談話や質疑がある。それは子どもにとって将来のイメージ形成に
極めて重要な役割を果たすと常々思っていました。
「部活動を学校から地域に移す」ことは、地域のおじさんやおばさん、お爺さんやお婆さんと
子どもたちが「ナマ」で接して、子ども自身が目指したいと思える「考え方や行動の模範となる人物」に
幅広く出会うことです。
今は、ご両親とか先生との接点があります。将来の夢は、学校の先生になりたいですとか、
入院して出会った看護師志望、ドラマの影響で検事や海上保安庁を目指します。
ですが、世の中はもっと多様化しています。動画とは違い、もっとリアルです。
キャリア形成の指針や成長のモチベーションにする大人を見つけることで、
夢は待っていれば降りてくるのではなく、自ら積極的に取りに行くエンジンになるはずです。
教員や警察官、政治家など大人の不祥事を子どもたちはしっかり見ています、
私たち大人も襟を正すチャンスです。